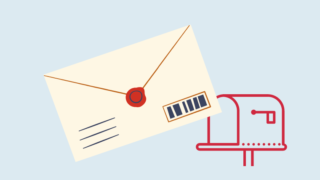家族が亡くなった場合、その人の財産は誰がどう引き継ぐのか?
相続が発生した時の話し合いや遺言書などについて、当事者として知っておきたいことをまとめました。
相続人とは?
相続人とは、法律上、亡くなった人の財産を受け継ぐ資格がある人をいいます。
| 遺言書による相続人 | 亡くなった人が、遺言書によって特定の人を指定した場合 |
| 法定相続人 | 法律で決められた親族(配偶者、子供、孫、親、兄弟姉妹など)が相続人となる |
遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合は、「民法」という法律に則って、誰がどういう順番で相続人になるか(法定相続人)が決まります。
相続人になる7つのパターン
亡くなった人の配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外は、相続人になる順番が決められていて、①子ども → ②親 → ③兄弟姉妹 となります。
たとえば、第1順位である子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は(子どもよりも順位が低いので)相続人にはなりません。
相続人となるパターンは以下のとおり。
- 配偶者+亡くなった人の子ども
- 配偶者+亡くなった人の親または祖父母
- 配偶者+亡くなった人の兄弟姉妹または甥・姪
- 配偶者のみ
- 子ども(または孫)のみ
- 親(または祖父母)のみ
- 兄弟姉妹(または甥・姪)のみ
子どもがいない夫婦の場合
子どものない夫婦のうち、たとえば夫が亡くなった場合、夫の家族の状況によって、相続人は以下のようになります。
| 夫の家族状況 | 相続人 |
|---|---|
| 両親と兄 | 妻と両親 |
| 親は他界、兄が健在 | 妻と兄 |
| 夫の親・兄ともに他界、夫の兄に息子がいる | 妻と、兄の息子(甥) |
配偶者の親・兄弟姉妹・甥姪も相続人に
子どもがいない夫婦の場合、夫の財産はすべて妻のものになると思われがちですが、遺言書がなく、民法に則って相続が行われると、「妻」と「夫の血族関係にある人」が相続人になります。
夫の親・兄弟がすでに亡くなっている場合は、その子孫が代わって相続人になるため、このケースでは妻に加えて、甥も相続人になるのです。
子どもがいない夫婦の注意点
亡くなった人の財産は、一旦相続人全員の「共有のもの」になります。
なので、妻とはいえ、勝手に夫の預金を引き出したり、不動産を処分することはできません。
遠方に住んでいたり、日頃ほとんど交流のない甥・姪であっても、まずは夫の財産を分けるために話し合いをしなければなりません。
スムーズに合意できれば良いですが、こんな場合は注意が必要です。
- 残された財産のほとんどが、不動産などの「分けにくい」ものだった。
- 残された財産には、甥が主張した分の現金がなかった。(自分の預金から用立てたり、自宅を売却しなければならない可能性も)
財産は不平等にしかならない
亡くなった人の配偶者・子・親・兄弟姉妹等は、財産を受け取る権利がある人(法定相続人)となり、残された財産を引き継ぐことになります。
それぞれの取り分のことを「法定相続分」といって、誰がどれくらいの割合で引き継ぐかの基準が、法律で定められています。
ただ、この割合はあくまでも目安で、必ずその通りに分けなければいけないものではありません。
遺産の中には、ケーキのように平等に切り分けることができないものも含まれます。
自宅などの不動産がその代表ですね。
むしろ分けられない、平等にならない方が普通です。
残された財産は、相続人同士がどういう風に分けるのかを話し合い、全員が合意した割合で分けて構いません。
その時に、数字(金額)上、平等になることにこだわるとタイヘンです。
そもそも「不平等にしかならない」と割り切って、話し合いをすることが大切です。
相続時の話し合いについて
相続人が多くても少なくても、残された財産を「どうする?」という話し合いは、必ずしなければなりません。
遺言書がない場合や、法定相続分とは違う分け方をする場合には、後々の手続きで、話し合った内容をまとめた書面(遺産分割協議書)が必要になり、合意したという証に、相続人全員の署名・押印が必要です。
相続人が遠くに住んでいるとか、協力的でない相続人がいる場合などは、かなりの時間と手間がかかることを想定しておきましょう。
遺産分割協議の注意点
亡くなった人の財産を、誰がどのように引き継ぐかを話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
- 遺産分割協議書は作成必須ではないが、相続手続きで提出を求められる場合は多いので、作成しておく方が良い。
- 話し合いは何度かに分けて行ったり、電話や書面でも可。最終的に相続人全員が合意しないと、遺産分割ができない。
- 相続人が海外に住んでいる場合は、住民票や印鑑証明に代わる特別な書類が必要。郵送にも時間がかかるため、期限のある手続き(相続放棄や相続税の申告)は要注意。
遺言書について
遺言書が残されている場合は、まず遺言書が優先されます。
遺言書は、亡くなった人の最終意思として、一番に尊重されるのです。
ただし、残す側として気をつけなければいけないのは、遺言書を書くことがゴールではないということ。
目指すは笑顔相続、家族がもめずにスムーズに相続する、そのために遺言書があります。
好きなように遺言書を書いて残せば万事OK!ではなく、逆に争いの種になってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
たとえ遺言書を残していても、相続人全員が同意すれば、遺言書とは違う内容で遺産を分けることもできてしまいます。
せっかくの思いがつまった遺言書でも、残される人の気持ちや状況とかけ離れていると、スムーズな相続に導く効果は少なくなってしまうんですね。
つまるところ、本当に伝えたいことは、元気なうちにしっかりと話をしておくことが大切なのだと思います。
法務局で保管可能な遺言書
自分で書いた「自筆証書遺言」は、法務局で保管してもらうことができます。
- 書いた遺言書の置き場所に困ったり、自分で保管して紛失してしまうリスクがなくなる。
- 封をする前の遺言書を持参し、形式不備がないかを確認してもらえる。(日付や押印がない等の不備があると、せっかく残しても無効になってしまうため)
- 遺言書を開封する際、家庭裁判所に出向いて行う「検認」という確認作業が必要ない。
遺言書には、形式ばった約束事だけではなく、付言事項(ふげんじこう)といって、自分の気持ちを綴ることもできます。
実際に遺された遺言書の付言事項を見てみると、家族への最後の思いにはすごく力があって、言葉で伝えるって素敵だなと思います。
遺言書というと堅苦しいイメージが先行してしまいますが、お世話になった人へのメッセージとして、ぜひ活用されることをおすすめします。
まとめ
家は長男が継ぐもの。
兄弟が何人いようと、家の財産は長男がすべて引き継ぐ(家督相続といいます)というルールが、その昔(昭和22年頃まで)存在していました。
生まれた順番が大きな意味を持っていた時代です。
時は流れて、時代は令和。
今では、財産は残された人でなるべく平等に分ける法定相続という考え方や、遺言書で受け継ぐ人を指定することが一般的になりました。
相続は頻繁に起きることではありませんが「いつかは来る」相続を、日頃のコミュニケーションの中で、たまに思い出してみてください。